【干支の順番と由来】読み方や覚え方は?十二支の漢字の意味は?
毎年巡ってくる、今年の干支(えと)。
干支は、もともと暦や方角に使う大事なものでしたが、今では、年賀状を書く時にしか意識しない方も多いかもしれませんね。
ところで、干支の由来についてはご存知でしょうか?
干支の順番が分かっても、その由来となるとあやふやではありませんか。
今回は、そんな干支の由来と順番についてご紹介します。
この記事の目次
干支(十二支)の順番は?読み方は?

干支の順番と読み方は次のとおりです。
この干支(十二支)には、それぞれ動物が当てられています。
年賀状などで、年毎に順番に使われる動物ですから馴染みがありますね。
それぞれがどの動物を指しているのか、ここで今一度確認しておきましょう。
『 丑(うし)』… 牛(うし)
『 寅(とら)』… 虎(とら)
『 卯(う)』… 兎(うさぎ)
『 辰(たつ)』… 龍(りゅう)
『 巳(み)』… 蛇(へび)
『 午(うま)』… 馬(うま)
『 未(ひつじ)』… 羊(ひつじ)
『 申(さる)』… 猿(さる)
『 酉(とり)』… 鳥(とり)
『 戌(いぬ)』… 犬(いぬ)
『 亥(い)』… 猪(いのしし)
干支の順番で簡単な覚え方はある?
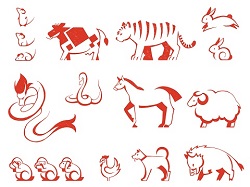
12種類ですから、繰り返し唱えれば覚えられると思います。
コツは、
『 ねー、うし、とら、うー、たつ、みー、うま、/
ひつじ、さる、とり、いぬ、いー 』
というように、【 / 】のところで息継ぎをすることです。
リズムが生まれて覚えやすいですよ。
もう少し細かくする場合は、「うー」と「とり」のあとに息継ぎを入れてもいいですね。
このほかに歌で覚える方法もあります。
メロディーがあるので、忘れにくいかもしれませんね。
十二支 簡単おぼえ歌!
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
ポンキッキーズ メロディ「十二支のうた」
記憶のコツはリズムよくポンポンつぶやくことです。
そうすると脳に容易に刷り込まれていき、いつのまにか覚えているようになりますよ。
干支の漢字の書き方は?どんな意味があるの?
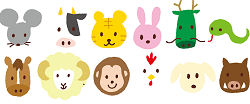
実は、十二支に使われている文字、子・丑・寅・卯などは、もともとは動物とはまったく関係のない字です。
十二支の漢字は、12の周期で月を表す記号でした。
記号の順番を覚えやすくするために、後から動物を割り振ったのです。
それぞれの漢字が本来表している意味は次のとおりです。
【丑(うし)】生命エネルギーのさまざまな結びつき。旧暦の12月。粘り強さと誠実さを表す。
【寅(とら)】形をとっての発生。旧暦の1月。万物の誕生を表す。
【卯(う)】さかんに茂るさま。旧暦の2月。家内安全や飛躍を表す。
【辰(たつ)】物がことごとく震い動いて伸びていく生の活動。旧暦の3月。権力や自然の活力を表す。
【巳(み)】とどまる、やめる、蛇の脱皮のように気の更新をする。旧暦の4月。生命力の強さや再生を表す。
【午(うま)】そむく、逆らう、上昇する陰と下退する陽とのぶつかり。旧暦の5月。社交性や人気を表す。
【未(ひつじ)】成熟して匂いや味がそなわる。旧暦の6月。家族や平和を表す。
【申(さる)】のびる、陰気が伸びて老いて成熟する。旧暦の7月。山の神の使いで信仰の対象。好奇心を表す。
【酉(とり)】壺の中で盛んに醗酵している状態。旧暦の8月。「とりこむ」ことから商売繁盛をあらわす。
【戌(いぬ)】茂るにつうじ、欲求不満が一杯になる。旧暦の9月。社会性や忠実さを表す。
【亥(い)】一杯になったエネルギーが一気に爆発し生命が充実。旧暦の10月。無病息災を表す。
それぞれ最初の意味合いを見ると、植物(命)が生長する順にもなっていますね。
本来の漢字の意味を知ると、十二支の順番にも納得ですね。
干支の順番が決められた由来は?

干支(十二支)の順は、先ほど漢字の意味と一緒に説明したとおりです。
でも、どのようにして、漢字に動物たちが当てはめられたのでしょうか?
そのいきさつは、「十二支の物語」に書かれています。
日本だけでなく、中国や朝鮮半島、モンゴル、ロシアなどひろく語り継がれているお話なんですよ。
十二支の物語 ~12の動物神様のもとへ向かう~
[十二支の順番]
子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
その昔、神様が動物たちに向かってこういいました。
「1月1日の朝に挨拶に来たものから順番に、12番目まで毎年交代でリーダーにする!」
それを聞いた動物たちはいろいろ考えながら、それぞれ挨拶するために出発しました。
牛は「自分は歩くのが遅いな」と感じていたので、ほかの動物達より早く行こうと前日の夜から歩きはじめます。
牛は出発も早く一番先に神様のところへ着くかもしれません。
そんな牛を見ていたネズミは一計を案じます。
それは牛の背中に乗ること。
気づかれないように牛の背中に乗っていれば、自分も早くに神様のもとへ着けるからです。
のんびりした牛の性格を見越して、こっそり背中に乗ったネズミは牛の歩みとともに神様のもとに向かいます。
思った通り牛は一番に神様のところに現れました。
前日から出発しているので、誰よりも早くに着いたのです。
“牛が一番!”と思った矢先、突如牛の背中からネズミが飛び出しました。
そして、牛が挨拶するよりも先に神様に挨拶をしたのです。
挨拶した順番で毎年リーダーになるというルールは変わりません。
そのため一番はネズミ、二番に牛の順番となりました。
しかし牛は2番になったことを怒りませんでした。
「2番で着ければ十分満足」として、文句一つ言いません。
ほかの動物たちはどうなったかというと、3番に着いたのは虎。
実は虎は、神様に挨拶した順番にリーダーになるという話を噂で聞いただけでした。
最初は信じていませんでしたので、参加するつもりはありませんでしたが、虎は思います。
「もしこの話が本当だったらビリは自分だ。そうなると赤っ恥をかくことになる。」
そして虎は疑いながらもレースに参加し、実は本当だったこのレースで、晴れて3番になることができました。
最初から参加していれば1番だったかもしれません。
4番目に神様のもとへ着いたのは兎(うさぎ)。
5番目は龍(竜)です。
なぜ兎は龍よりも早くに着けたのでしょうか。
それは兎はみんなが途中で休んでいる間も、懸命にピョンピョンと進んでいたからです。
5番目は龍ですが、本当は巳(へび)と同着でした。
龍は空をとぶことができて、毎日修行も積んでいます。
巳(へび)はそんな龍を尊敬し、龍に順番を譲ったのです。
こうして5番目は龍(竜)、6番目は巳(へび)となりました。
午(うま)と未(ひつじ)は周りに関係なく、マイペースで進んでいきます。
結果、足の早い午(うま)の方が未(ひつじ)よりも早く着き、7番目に午、8番目に未となりました。
次に猿、酉(とり)、戌(いぬ)の順番となりますが、なぜこうも到着するのが遅かったのでしょうか。
それは猿と戌(いぬ)が喧嘩をしていたからです。
その喧嘩の間に入って止めていたのが酉(とり)。
なのでこの3匹は神様のところへ着くのに時間がかかってしまったのです。
最後の到着したのは亥(いのしし)となりますが、そんなに遅かったのかというとそうではありません。
実は亥(いのしし)は、すごいスピードで神様の元へ突っ走り、誰よりも早く着いていたのです。
ところが勢い余って、神様のもとを過ぎてはるか先に行ってしまいました。
神様のところへ戻ったときには皆がゴールした後だったというわけですね。
こうして干支の順番は、【 子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥 】となりました。
干支の漢字の由来と、十二支の物語

【関連記事】
●年女年男の意味とは。縁起は?厄年の場合は厄払いが必要?
●おみくじの順番と意味。半吉や末吉は?地域別の呼び方は?
干支の由来や順番についてお送りしました。
干支が、もともと動物には全く関係がない漢字だったなんて意外ですね。
干支の漢字の由来や十二支の物語は、ちょっとした豆知識として覚えておくと、新年の話題になりますよ。
