【小暑2025年の時期と意味】小暑の候の例文は?暑中見舞いは?
『暑い』という言葉を頻繁に見聞きにするようになったら、本格的な夏の到来ですよね。
ただ一言に暑いといっても、その暑さには時期によって違いがあります。
たとえば、「梅雨のじめじめした暑さ」と「梅雨明け後の太陽が照りつける暑さ」は、まるで別物ですね。
そんな体感の違いを表す言葉が、日本には数多くあります。
今回はその中から、『小暑』の時期や意味、小暑の候の例文などをご紹介します。
“ 小さい暑さ ” なので、夏の初め頃のことかな?と想像はつきますが、小暑という言葉を使うことができる時期はきちんと決まっていますよ。
この記事の目次
小暑の読み方や意味は?

まず、小暑と書いて「 しょうしょ 」と読みます。
その名のとおり、大暑の前にやってくる季節という意味で、本格的な暑さを迎える目安でもあります。
近年では、梅雨入り前から夏のような暑さを感じる日もありますが、小暑が来る前に体力をしっかりつけて、夏の対策は万全にしておきたいですね。
小暑2025年の時期や期間は?
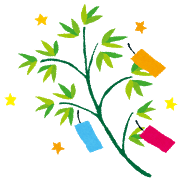
小暑の時期は七夕である7月7頃で、期間は次の二十四節気(にじゅうしせっき)である大暑までの間を指します。
正確には直前の夏至から数えて15日目が小暑にあたるので、年によって多少のバラつきはありますが、七夕は小暑と同時期となります。
小暑は二十四節気の11番目で、前後の順番は、夏至 → 小暑 → 大暑 となっています。
本来、梅雨が明け太陽の照りが強くなり本格的な夏になり始める頃ですね。
ちなみに、梅雨入りの最終ラインは小暑が目安で、この日までに梅雨入りしない場合はその年の梅雨はなしと判断されるそうですよ。
梅雨がないのは嬉しいですが、農作物にとって雨はとても大切なので、その後の作物の育ち具合に大きく影響します。
秋においしい野菜や果物が食べられなくなる、もしくは値段が高騰すると思うと複雑な心境ですね。
2025年の小暑の時期や期間は?
2025年および、今後3年間の小暑の時期と期間はこちら。
[2025年 小暑の時期]7月7日(月)
〔2026年〕7月7日(火)
〔2027年〕7月7日(水)
〔2028年〕7月6日(木)
2025年、大暑(小暑の次)は7月22日となっていますので期間はこちら。
[2025年 小暑の期間]7月7日(月)~21日(月祝)
小暑の七十二候は?

小暑は二十四節気の11番目で、夏至 → 小暑 → 大暑 の順番であるとお伝えしました。
そして二十四節気はさらに細かく七十二候に分かれています。
小暑をさらに3つに分けた期間についてご紹介します。
温風至(おんぷういたる・あつかぜいたる)
7/7~12頃:夏の熱い風が吹いてくる時期。
梅雨明けころに吹く風は白南風(しろはえ)といいます。
雷雲が発生しやすい頃でもありますね。
旬の野菜:ゴーヤー、とうがん、へちまなどはビタミンCやカリウムが豊富で夏バテ対策に効果的。
旬の魚:こち‥高タンパク、低脂肪で夏バテ対策に効果的
旬の行事:ほおずき市
蓮始開(はすはじめてひらく)
7/13~17頃:蓮の花が咲きはじめます。
旬の野菜:とうもろこし‥ひげが多く、毛先が茶色いものがおすすめ
旬の魚:かれい‥別名は、おちょぼ、くちぼそ、など
旬の虫:アゲハチョウ
旬の行事:迎え火
鷹乃学習(たかすなわちがくしゅうす・たかわざをならう)
7/18~22頃:鷹の子が飛ぶ練習をはじめます。
夏の土用は立秋前の18日間で7/20頃土用入り。
丑の日が土用の丑の日で、年に2回ある場合は、一の丑、二の丑とよびます。
旬の野菜:モロヘイヤ‥ビタミン、ミネラル豊富
旬の魚:うなぎ‥ビタミンAやDが豊富で夏バテや夏痩せに効果的
旬の野鳥:ハチクマ
小暑の候 使う時期や例文は?

小暑の候が適切な時期
ビジネス文書の挨拶で使われる○○の候ですが、7月の挨拶には小暑が使われます。
先ほど述べたように七夕の時期を指す言葉なので、適しているのは7月初旬ということになります。
親しい方へのお便りや、少しくだけた文章で7月初旬の挨拶を書く場合は、天の川が美しい季節に~や、七夕飾りを目にする季節に~など、小暑と同じ時期を意味する七夕の行事に絡めた書き出しが素敵だと思います。
小暑を使った例文
一般的なのは、やはり「小暑の候」です。
などと使いますね。
また、7月上旬のお便りだけど七夕は過ぎてしまったという微妙な時期の場合は、「小暑を過ぎて」という表現が便利です。
『 小暑を過ぎて、夏本番がやってまいりました。』
梅雨が長引いている場合はこのように梅雨見舞いでも良いでしょう。
『 小暑を過ぎて、梅雨明けを待つばかりとなりました。』
など、バリエーションをつけることができます。
今の季節に対して感じていることを交えて書き始めると、親しみやすく自分らしい文面になると思いますよ。
暑中見舞いは小暑の時期に出しても大丈夫?

暑中見舞いを出す時期はいくつか説があり、どれが正しいかは判断がしにくいようです。
一般的には梅雨明けの時期が目安とされていますが、地域によって差が出るので、受け取る側の梅雨明けを調べてから出す必要があります。
小暑から出してもいいという説もあるのですが、近年の梅雨明けは本州で7月19日前後なので、まさに夏土用の時期と一致します。
小暑は梅雨明けにはまだ早いので、暑中見舞いを出すのは少し待ったほうがいいかもしれません。
暑い時期に相手の体調を気遣う意味をもつお便りなので、小暑の頃から準備をして、夏土用に合わせて届くように送りたいですね。
ちなみに立秋以降は残暑見舞いとなります。
小暑は夏の訪れを感じる言葉

【関連記事】
小暑の時期や意味、使い方などをお送りしました。
小暑は、本格的な梅雨と本格的な夏の間に挟まれた時期を意味する言葉です。
そんな狭間の季節にも名前をつけている国は、なかなか珍しいのではないでしょうか。
生活のあらゆるところに根付いた繊細な芸術性を感じますね。
ともすれば気づかぬうちに通り過ぎてしまいそうな小暑ですが、実はとても大切な時期かもしれません。
湿度の多い暑さからカラッとした暑さへと移り変わる時期は、体調を崩しやすく少し過ごしづらいもの。
小暑の間に心と体を整えることを意識して、キラキラと眩しい夏本番へ向かっていきましょう。
